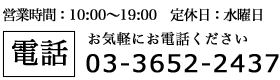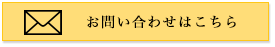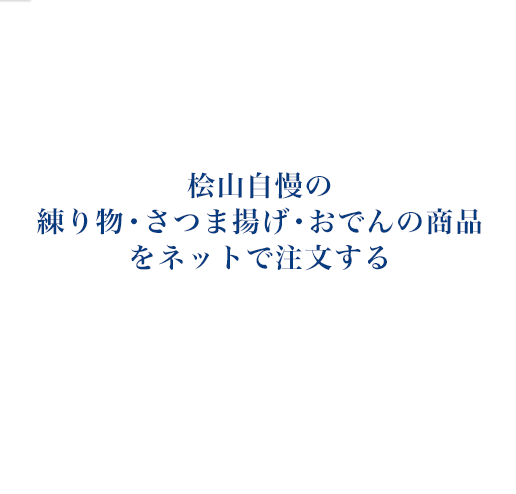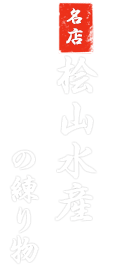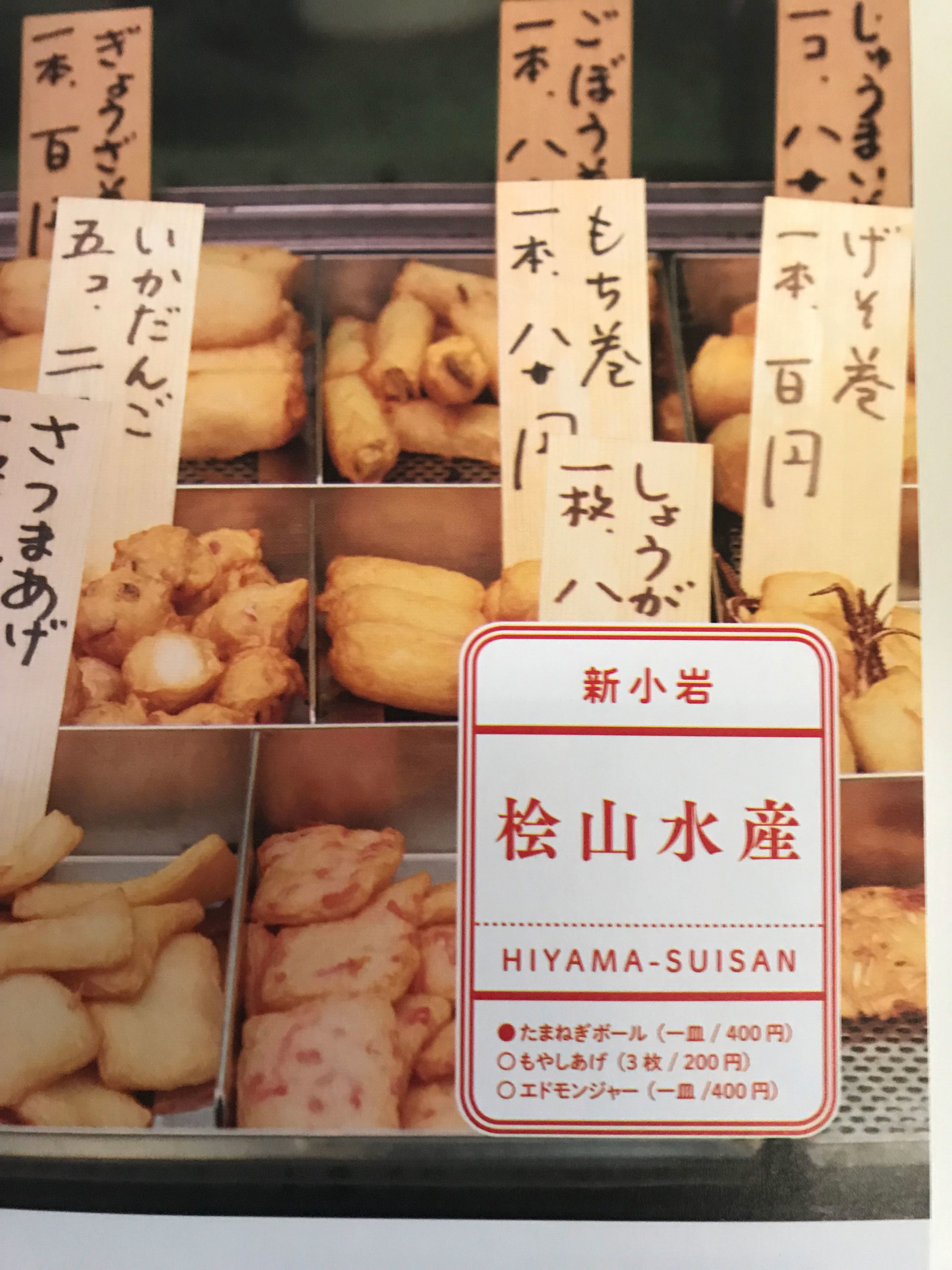
薩摩揚げは、中国由来の料理が琉球に伝わり、薩摩を経由して全国に広がったとされています。
鹿児島、沖縄県では一般につけ揚げと呼ばれています。
関東では、さつま揚げ、西日本では、てんぷらとも呼ばれています。
さつま揚げは、まだ冷蔵技術が発達していなかった時代に、地元で獲れた魚を有効利用するために生まれたため、さつま揚げに使われる魚の種類は多岐にわたります。
主に使われる魚はスケソウダラ、エソ、グチ、イワシ・サメ・カツオ・サバ、トビウオなどですが、
この以外の魚が使われることも珍しくありません。
すり身のみで作られた物のほかに、きくらげ、紅しょうが、玉ねぎ、ネギなどの野菜を入れたもの、じゃこ、イカ、タコ、エビなどの魚介類を入れたもの、薬味を加えたものなどもあります。
当店ではスケソウダラ、イトヨリダイを使用しています。